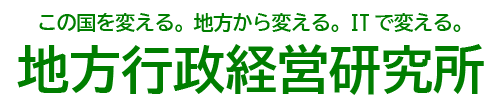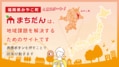サステナブルなデータ分析、実現していますか?
データ提供者及びデータ分析者が得ることができる便益とは
6. 分析結果をどのように発展させていくべきか
官民データ活用推進基本法では、官民データ活用の推進は「効果的かつ効率的な行政の推進に資することを旨として、行われなければならない」とされていますが、民間企業からデータの提供を受け、大学が分析を請け負っている以上、彼らに対しても何らかの便益がなければ継続可能な取組にはならず、一過性の取組に終始してしまうでしょう。官民データ活用の取組は短期的に大きな効果をもたらすものではなく、中長期的に改善を積み重ねてもたらす効果を大きくしていくものだとすれば、継続策を考えなければなりません。そこで、民間企業にとって今回の分析結果が有益であったか、大学にとって滋賀データ活用LABの取組が有益であったかを聞いた上で、彼らがそれぞれどのような便益を期待しているのか、官民データ活用はどのような便益を提供し得るのかを考えてみたいと思います。
(1) 観光・交通分野
事務局、データ提供者及びデータ分析者の中から、観光・交通分野のデータ分析において中心的な役割を果たした関係者に反応を聞きました。
① 観光・交通分野の分析結果は近江鉄道株式会社にとって有益なものだったか
滋賀データ活用LABの分析結果が有益であったか、近江鉄道株式会社の深尾課長に聞きました。
■続きは以下のページから
https://lg-institute.gyoseiq.co.jp/blog/member/chief_30-2