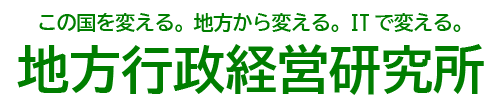限られたデータからどのようにして有益な結果を得たのか?
有益な結論を得るためのテーマ設定や分析内容、環境
5. 分析するためにどのような環境を整備すべきか
滋賀データ活用LABの取組においては、事務局やデータ提供者が分析テーマを設定せず、あくまでもデータ分析者に委ねられています。分析を請け負った各者は、提供されたデータと自らの専門分野からどのようなテーマを設定し、どのように分析を行い、どのような結論を得たのでしょうか。データ分析者に委ねても、事務局やデータ提供者にとって有益なテーマが選定されるのでしょうか。提供されるデータに制約があっても、有益な結論が得られるのでしょうか。また、そのためにどのような環境でデータを分析する必要があったのでしょうか。どのような事前準備や利用規約を必要としたのでしょうか。各者に聞きました。ただし、滋賀データ活用LABでは全ての分析内容を公表していません。研究発表会における抜粋資料(各4スライド)を紹介します。
(1) 立命館大学(塩見研究室)
観光・交通分野の分析を請け負った立命館大学の塩見氏に、分析の概要について聞きました。
――提供されたデータから、塩見研究室ではどのようなテーマを設定し、どのように分析を行い、どのような知見が得られましたか。
■続きは以下のページから
https://lg-institute.gyoseiq.co.jp/blog/member/chief_28-2